医師・医療従事者様へ
医薬品の個人輸入について解説
01医薬品の個人輸入とは?
医療機関・医師による輸入は
「個人輸入」扱いになるのか
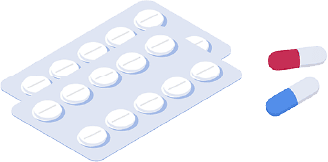
医師や医療機関が海外から未承認の医薬品を輸入する際も、法律上は「個人輸入」という形で取り扱われます。
日本では医薬品の使用および流通は、医薬品医療機器等法(薬機法)により厳しく規制されており、原則として厚生労働省の承認を受けた医薬品のみが国内で流通・使用できます。
ただし、医師が治療上必要と判断した場合に限り、未承認薬を診療目的で輸入することが可能です。
この場合、個人輸入に準じた取扱いがなされ、自家使用または特定の患者への使用に限って、輸入確認証(いわゆる「薬監証明」)を取得することで輸入が認められます。
なお、商業目的での販売や譲渡は禁じられており、一定の条件(国内に代替薬がないこと、患者の同意取得等)を満たす必要があります。
一般の個人輸入との違い

一般消費者による個人輸入は、たとえ治療目的であっても、医薬品に関する十分な知識や使用管理が伴わないことから、安全性や健康被害のリスクが指摘されています。
医療機関が患者の治療の一環として未承認薬を用いる際は、薬機法上の輸入手続(例:薬監証明の取得)を適切に踏むことで、法的に許容された形で輸入・使用することが可能です。
02医師が行う医薬品の個人輸入の注意点
誰が輸入できるのか
(医師・歯科医師・医療機関)
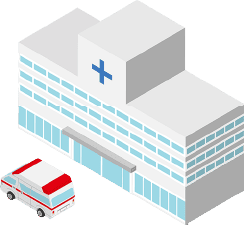
医薬品の輸入は、原則として医師・歯科医師・医療機関が患者への治療目的に限り可能です。一般の個人輸入とは異なり、営利目的や第三者への譲渡・販売は禁じられています。
医師・歯科医師は、自らの責任において自身の治療行為に必要な範囲でのみ輸入できます。医療機関は法人として輸入する場合も同様に、最終的に医薬品を使用する医師・歯科医師が当該医薬品の適正使用について責任を負い、その資格(医師免許・歯科医師免許)を有している必要があります。
治療目的での使用とその要件

輸入した医薬品を治療目的で使用する際は、「緊急性があり、かつ他に代替治療法が存在しない」などの合理的理由が求められます。
また、治験薬や研究段階の薬剤を除き、輸入薬が一定の治療効果を期待できるものであることが前提です。厚生労働省はこのような使用をあくまで例外的に認めており、常用的な使用や院内標準治療として位置付けることは原則として適しません。医師は、これらの医薬品を使用するにあたり、患者に対して、未承認医薬品であることのリスクや副作用、代替治療法の有無などについて十分に説明し、インフォームドコンセントを得る必要があります。
患者のための輸入か、
自己の診療行為のためか

個人輸入は、自らの診療に使用する目的でなければ認められません。
医師が他の医師や第三者に譲渡する目的で輸入することは法律上禁じられています。
あくまでも自らの責任の下で診療に使用する目的に限られます。
また、患者本人が輸入者となる場合には、輸入サポートを医療機関が担うことも可能ですが、その際にも薬機法違反とならないよう配慮が必要です。
輸入数量の制限について
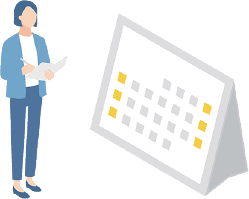
個人輸入できる医薬品の数量にも制限があります。原則として1回の輸入につき、1か月分程度の使用量が目安とされており、必要に応じて2~3か月分まで認められることもあります。
ただし、それ以上の数量を輸入する場合には、薬監証明の取得が必須となる場合があり、また過剰な輸入は商業目的と見なされて違法となる恐れがあります。
輸入数量の妥当性は、税関や厚労省の指導によって変動することもあるため、事前に専門業者に相談するのが安全です。
03医薬品の個人輸入に関わる関税・通関
医薬品輸入時にかかる関税とは

医薬品を個人輸入する場合、通常の商品と同様に関税や消費税などが課税されることがあります。
ただし、日本では医薬品に対する「関税率」は非常に低い、もしくは無税とされているケースがほとんどです。
そのため、実質的に支払うことになるのは「消費税(および地方消費税)」が中心となります。
課税対象となるのは、輸入品の価格(CIF:商品価格+保険料+運賃)に対して8%または10%が課せられるケースが一般的です。
関税が免除されるケース

医師や医療機関が診療目的で医薬品を輸入する場合でも、輸入品の価格が一定額以下であったり、使用目的が明確に「個人使用」として認められる場合には、関税や消費税が免除されることがあります。
たとえば、課税価格が1万円以下の小口輸入は「少額輸入免税制度」の対象となる可能性があり、非課税扱いとなることもあります。
ただし、繰り返しの輸入や高額な薬剤などは課税対象となりやすく、必ずしもすべてが免除されるわけではありません。
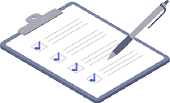 税関で必要となる書類(薬監証明、インボイスなど)
税関で必要となる書類(薬監証明、インボイスなど)
医薬品の輸入時には、以下の書類を税関に提出する必要があります。
-
インボイス(納品書・請求書)
品目名、数量、金額、出荷元情報
などが記載された書類 -
パッキングリスト
梱包内容の詳細
-
薬監証明
(輸入確認証)未承認医薬品を輸入する際に
厚労省が発行する輸入確認証 -
輸入者情報の
確認書類医師免許証の写しなど
書類が不備の場合、通関手続きが遅延し、最悪の場合は薬品が差し押さえられることもあります。
 税関でのトラブル事例と回避方法
税関でのトラブル事例と回避方法
実際には、下記のようなトラブルが発生することがあります。
-
インボイスの記載ミスにより、関税額が過大評価される
-
薬監証明(輸入許可証)が必要な薬品なのに添付がなく、輸入差し止めとなる
-
法人名義で個人輸入を試みたため
通関が拒否される
これらを回避するためには、事前に必要な書類を確認・準備し、薬機法および関税法に精通した業者のサポートを受けることが重要です。
当社ではこれら通関上のトラブルを回避するため、インボイス作成の指導や薬監証明取得の代行も行っており、安全かつスムーズな輸入を支援しています。
04医薬品個人輸入の法律(薬機法・関税法など)
薬機法上の「個人輸入」の定義と制限

日本では、医薬品の製造・販売・輸入に関して「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法)」が適用されます。
薬機法では、厚生労働省の承認を受けていない医薬品の国内流通・販売は原則として禁止されていますが、「個人輸入」という例外規定により、自己の使用目的に限って未承認医薬品の輸入が認められています。
医師や医療機関による診療目的の輸入も、あくまで患者個人の治療に必要な範囲に限り「個人輸入」として許容されます。
認可・承認されていない医薬品の扱い
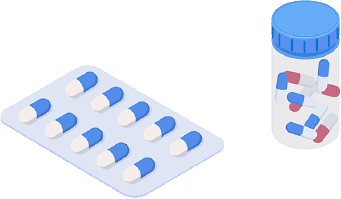
厚労省の承認を受けていない未承認医薬品を使用する場合には、適切な診療上の理由と医師の責任が求められます。
また、患者の安全性や治療効果について慎重な判断が必要です。
特に、海外で市販されている医薬品であっても、日本での医療的エビデンスや安全性に関する情報が不十分なものは、患者に深刻な副作用をもたらす可能性があります。
こうしたリスクを理解したうえで、十分なインフォームドコンセントが求められます。
医薬品の個人輸入が違法となるケース
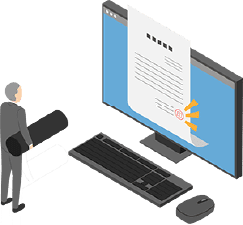
医薬品の輸入時には、以下の書類を税関に提出する必要があります。
- 医師であっても、他の医師や患者に「販売」「譲渡」を目的とした輸入を行った場合
- 医師であっても、他の医師や患者に「販売」「譲渡」を目的とした輸入を行った場合
- 許可なく向精神薬・麻薬などの規制薬物を輸入した場合
- 医師免許を持たない者が患者に対して医薬品を個人輸入し、診療行為を行う場合
これらは薬機法だけでなく、関税法や麻薬取締法などにも抵触する可能性があります。
許可なく輸入・販売することのリスク

医療機関が承認を得ずに未承認薬を販売したり、複数の患者に使用する目的で輸入した場合、「無許可販売」や「無承認医薬品の流通」として法的リスクが高くなります。
たとえ善意であっても、手続きを踏まない輸入・販売は、行政処分や業務停止、さらには刑事罰の対象となる可能性があります。
患者に使用する際の法的責任とインフォームドコンセント
これらを回避するためには、事前に必要な書類を確認・準備し、薬機法および関税法に精通した業者のサポートを受けることが重要です。
当社ではこれら通関上のトラブルを回避するため、インボイス作成の指導や薬監証明取得の代行も行っており、安全かつスムーズな輸入を支援しています。
05薬監証明(輸入確認証)とは?
輸入時に必要なケースと不要なケース
薬監証明(正式名称:輸入確認証明書)は、厚生労働省が発行する書類で、未承認医薬品や再生医療等製品、医療機器などを輸入する際に必要となる確認証明書です。すべての医薬品輸入に必要なわけではなく、以下のようなケースで必要となります。
-
case1
医師・医療機関が自らの診療目的で未承認薬を輸入する場合
-
case2
医療法人や病院名義で輸入を行う場合
-
case3
1か月分を超える医薬品を一括で輸入する場合
-
case4
厚労省が指定する特定の成分や薬剤(例:ホルモン剤や抗がん剤など)を含む場合
一方で、個人が自己使用目的で少量輸入する場合(例:1か月分以内の輸入など)には、薬監証明が不要とされるケースもあります。
詳しくはこちらのページをご確認ください。
 弊社による申請サポートについて
弊社による申請サポートについて
当社では、医療機関向けに薬監証明の申請サポートサービスを提供しています。具体的には以下のような支援を行っております
-
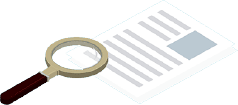
薬監証明が必要かどうかの事前確認
-

申請書類の作成サポート
(用途説明書・英文資料の翻訳対応も可能) -

地方厚生局対応のフォローアップ
-
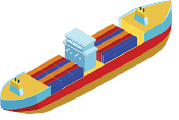
通関手続きとの連携によるスムーズな輸入支援
初めての申請でもスムーズに進行できるよう、経験豊富なスタッフがサポートいたします。
時間のロスやトラブルを防ぐためにも、薬監証明が必要な場合はぜひ当社までご相談ください。
06弊社のサポート内容と安心の理由

医療機関向け個人輸入サポートの実績
当社は、医師・歯科医師・クリニック・病院などの医療機関を対象に、医薬品の個人輸入支援を専門に行っている代行業者です。
これまでに多数の医療現場で必要とされる未承認医薬品の輸入サポートを行ってきた実績があり、特に治験薬、希少疾病用医薬品、代替治療薬などの分野で多数の対応経験があります。
医師の診療方針に合わせた輸入計画の提案や、必要な手続きに関するアドバイスを通じて、安全かつ合法的な輸入手続きを支援しています。

書類準備から通関対応まで一貫支援
医薬品の個人輸入には、薬監証明の申請、税関手続き、インボイスや用途説明書の作成、通関業者との連携など、煩雑なプロセスが伴います。
当社では、これらすべての工程をワンストップで支援。厚労省や税関の要件に準拠した書類の整備や、通関トラブルを未然に防ぐためのリスクチェックも行い、医師の業務負担を最小限に抑えるサポート体制を整えています。
また、特定の薬剤については、通関時に生じやすい課税誤りや通関遅延にも事前に対応。
状況に応じて、輸入ルートの変更や出荷元の調整などもご提案いたします。

海外メーカーとの英語対応も可能
輸入する医薬品のほとんどは海外製であり、製造元・販売元との連絡には英語での対応が必要になります。
当社では、英語でのメール交渉・書類取得・翻訳作業も含めて代行可能です。メーカーやディストリビューターとのやり取りに不安を感じる医療機関様でも、安心してご依頼いただける体制を整えております。
加えて、成分表・製品説明書の翻訳や、薬監証明用の用途説明書の作成支援など、専門性の高い医薬関連文書にも対応できるスタッフが在籍しております。
